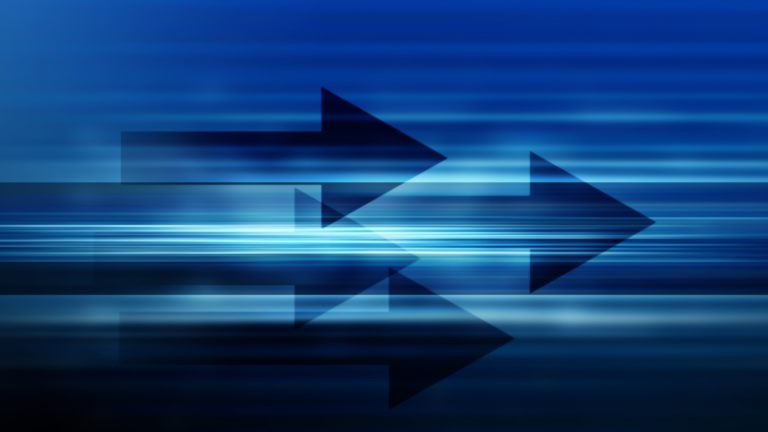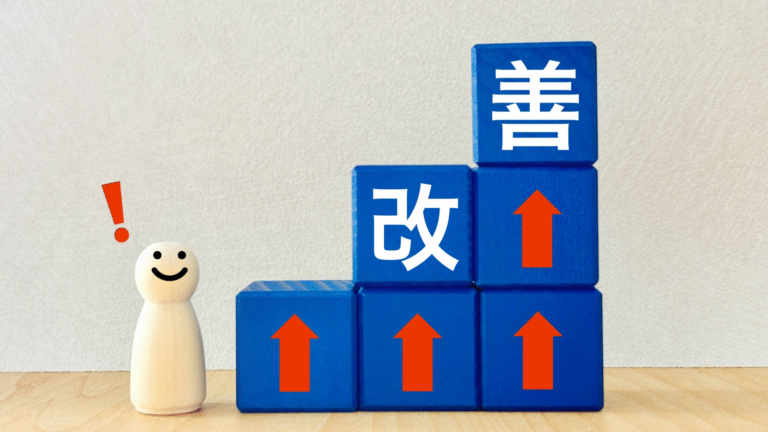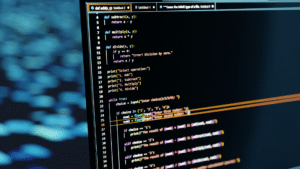Column オフィスITのお役立ちコラム
ITのお悩み・最新トレンドをやさしく解説。
業務に役立つノウハウを発信しています。
2025.09.19
IT担当の不在に強い環境を作る!見える化・属人化防止・定期点検のやり方

「うちには専任のIT担当はいないけど、これまで何とかなってきたから大丈夫」と考えているうちに、業務の停滞や情報漏えいといった見えないリスクがどんどん大きくなっているかもしれません。とくに気をつけたいのは、IT回りを主に担っている担当者が休職・退職したときに発生する混乱です。
ここでは、IT担当がいないことで生じる具体的な問題から、今日から始められる実践的な対策、そして将来を見据えた体制づくりまで解説します。
IT担当がいないと起きること
IT担当者が不在、あるいは特定の社員が兼任している状況は、日常業務の停滞からハッキングによる情報流出まで、さまざまな問題を引き起こすかもしれません。ここでは、IT担当がいないことで具体的にどのような問題が起きるのか、4つの側面から解説します。
ちょっとした不具合が大きな時間ロスになる
「プリンタで印刷ができない」「Wi-Fiが頻繁に途切れる」「Web会議の音声が聞こえない」などの些細に見えるこれらのトラブルも、IT担当者がいない環境では業務全体を止めてしまう大きな要因になります。
■初動が遅れ、解決までの道のりが長い
……トラブルが発生すると、当事者が誰に聞けばよいかわからず右往左往したり、複数の社員が手探りで対応にあたったりすることで、不要に時間を消費することになります。やっとの思いで外部の業者に連絡しても、状況を正確に伝えられず、解決がさらに遅れるケースも珍しくありません。
■同じ質問の繰り返しで生産性が低下
……トラブルの解決方法が社内に蓄積されないため、同じようなトラブルが起きるたびに、ゼロから調査や対応を始めることになります。複数のベンダーやサービスを利用している場合だと、どこに責任があるのか切り分けができず、問い合わせ先をたらい回しにされてしまうことも少なくありません。
退職者アカウントや更新忘れが「見えない穴」になる
IT担当者がいないことで最も危険なのが、セキュリティ管理の不備です。目に見えないところで、会社の信用を揺るがしかねない深刻なリスクが進行している可能性があります。
■退職者のアカウントが“野放し”に
……社員が退職した後も、その社員が使っていたメールアカウントやクラウドサービス(Google DriveやMicrosoft 365など)、業務システムへのアクセス権が残ったままになっていることがあります。放置していると、悪意のある第三者による不正アクセスや、元社員による情報持ち出しにも気づけません。
■更新されないソフトウェアが“侵入口”に
……パソコンのOSやソフトウェアの更新(アップデート)は、機能追加だけでなく、セキュリティ上の弱点(脆弱性)を塞ぐために不可欠です。IT担当がいないと、これらの更新が後回しにされたり、社員任せになったりしがちです。古い状態で放置されたシステムは、ウイルスやランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の格好の侵入口となります。
拠点やテレワークが増えるほど混乱が増える
働き方の多様化は、IT担当者不在のリスクをさらに増大させます。本社にいれば何とかなっていたことも、支社や在宅勤務環境では通用しなくなるのです。
■セキュリティレベルにムラが出る
本社と支社、あるいは社員の自宅とでネットワーク環境がバラバラだと、セキュリティレベルにムラが生まれます。MDM(モバイルデバイス管理)のようなしくみがなければ、端末を遠隔でロックしたりデータを消去したりすることもできません。
■管理が複雑化し、トラブルが長期間放置されやすくなる
各拠点でバラバラに通信回線や機器を契約していると、管理が煩雑になりトラブル時の対応も遅れます。勤務時間や場所が異なると、これまでのように「隣の席の詳しい人に聞く」という解決策も使えなくなり、問題が長時間放置されることになります。
IT知識を持つ人に負担が偏る
IT担当者がいない会社でよく見られるのが「ITに少し詳しい」というだけの理由で、特定の社員に問い合わせが集中するケースです。このようにしてIT知識のある一部の人だけに業務が集中すると、次のような問題があります。
■兼任担当者の疲弊と本来業務の遅延
……その社員は、親切心から対応しているうちに、いつの間にか“事実上のIT担当者”になってしまいます。しかし、あくまで兼任であるため、ひっきりなしに来る問い合わせに対応するうちに、自身の本来業務がどんどん後回しになっていきます。結果として、心身ともに疲弊し、モチベーションの低下や最悪の場合、離職につながることもあります。
■属人化によるブラックボックス化
……社内の「詳しい人」が休暇を取ったり、退職してしまったりした途端、社内のIT業務は完全にブラックボックス化します。トラブル解決のノウハウはもちろん、各種サービスのパスワードや契約情報さえもわからなくなり、事業継続に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
まずはIT環境の「見える化」をする

IT担当者不在の状況から脱却するための第一歩は、今の状況を正しく把握することです。まずは社内のIT環境を「見える化」し、漠然とした不安を具体的な課題に変えていきましょう。
具体的には、以下のような作業で十分です。
- パソコン・スマホ・使っているサービスを1枚に書き出す
- 自動更新・バックアップ・多要素認証をONにする
- 使っていないアカウントを止める・有パスワードを替える
- 困ったときの相談窓口を一本化しておく
パソコン・スマホ・使っているサービスを1枚に書き出す
まず、社内で使っているIT資産をすべて一枚のシートに書き出すことから始めます。これは「IT資産管理台帳」と呼ばれるもので、エクセルなどの表計算ソフトで十分作成可能です。この台帳が、今後のIT管理における地図の役割を果たします。
最初に、会社が所有するパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末情報を一覧にします。「誰が、どの端末を、どこで使っているか」を基本に、機種名やOSのバージョンまで記録しておくと、後の管理が格段に楽になります。
次に、社内で利用しているソフトウェアやクラウドサービス(SaaS)を棚卸しします。会計ソフトや顧客管理システムはもちろん、各部署が独自に契約しているツールも対象です。それぞれの「用途、契約プラン、管理者、更新期限」を記録します。
自動更新・バックアップ・多要素認証をONにする
IT資産の全体像が見えたら、次は基本的な防御設定を見直します。これらは、専門知識がなくてもすぐに実行でき、セキュリティレベルを大きく向上させることができる重要な設定です。
パソコンのOS(WindowsやmacOS)やソフトウェアの更新は、機能追加だけでなく、セキュリティ上の弱点(脆弱性)を修正する大切な役割があります。これらを常に最新の状態に保つため、自動更新設定がONになっているか必ず確認してください。
トラブル発生時に社内の大切なデータが消えるリスクへの備えとして、バックアップ(データの予備をとっておく作業)は不可欠です。重要なファイルが保存されているサーバーやパソコンのデータが、定期的に別の場所(クラウドストレージや外付けHDDなど)へ自動でコピーされる設定になっているか確認しましょう。
さらに、IDとパスワードだけに頼らない「多要素認証(MFA)」の導入も強く推奨します。これは、ログイン時にスマートフォンへ送られる確認コードの入力などを追加することで、不正ログインを格段に防ぐことができるしくみです。とくに管理者権限を持つアカウントは、最優先で設定してください。
使っていないアカウントを止める
管理が行き届いていない環境では、使われなくなったアカウントや安易なパスワードが、セキュリティの穴になっていることがよくあります。この機会に、アクセス権限の総点検を行いましょう。
最も危険なのが、退職した社員のアカウントが有効なまま放置されているケースです。これは、会社の重要情報への「裏口」を開けっ放しにしているのと同じ状態です。直ちに棚卸しを行い、不要なアカウントはすべて停止または削除してください。
困ったときの相談窓口を一本化しておく
トラブルが発生したときの「誰に聞けばいいかわからない」「あちこちに連絡して時間がかかった」という事態を避けるため、社内の問い合わせ窓口を一本化しましょう。
問い合わせ窓口の設置では、正式に担当者や担当部署を用意できなくても構いません。まず「ITに関する困りごとは、まずこのメールアドレス(またはチャットグループ)に連絡する」というルールを決め、全社に周知します。
設置した窓口での対応をスムーズにするため、トラブルの緊急度もあらかじめ設定しておきましょう。たとえば「全社のネットワークが停止した」といった緊急事態と、「個人のマウスが動かない」といった問題では、対応の優先順位が異なります。簡単な優先度基準を設けておくと、対応する側も判断がしやすくなります。
IT業務が属人化しないルールをつくる
IT環境の「見える化」ができたら、次はその状態を維持し、誰もが同じ品質で業務を遂行できるしくみを作ります。担当者が変わっても業務が止まらない、持続可能な体制を目指しましょう。
IT業務の属人化を避けるルールとしては、以下のようなものが適切です。
- パスワードと権限について決める
- IT台帳の型を用意する
- 入社・退職のチェックリストで漏れをゼロにする
- 社内IT相談の方法をテンプレート化する
- 月に一度の軽点検日をカレンダーに固定する
パスワードと権限について決める
セキュリティの根幹をなすのが、パスワードとアクセス権限の管理です。ログイン情報やそれぞれのアクセス権限は、全社で守るべきルールを決めましょう。
パスワードの作成と運用は「複雑なものを作成し、使い回さず、多要素認証で守る」のが定石です。例として、次のようなルール作りが考えられます。
- パスワードを作成するとき:8文字以上、英数記号を混ぜる
- パスワードの管理:ほかの社員に教えない、使い回しもしない
- ログイン時の設定:社用携帯に入れたアプリによる二段階認証を必須とする
社員のアカウントに与える権限は、その人の役職や業務内容に応じて、本当に必要な範囲だけに限定する「役割ベースのアクセス制御」(RBAC)の考え方が基本です。これにより、意図しない操作や情報漏えいのリスクを低減できます。
IT台帳の型を用意する
「見える化」のステップで作成したIT資産のリストは、継続的に更新・活用できる「IT台帳」へと進化させましょう。作成した台帳は、トラブル対応からコスト管理、将来計画まで、あらゆる場面で役立つ基盤情報となります。
台帳には、PCやサーバーといった物理的な機器だけでなく、次のようなものも記載します。
- ソフトウェアのライセンス
- クラウドサービスの契約
- ネットワーク回線の情報
それぞれの資産には、購入・契約から廃棄・解約までのライフサイクルを追跡できるように、購入日または契約日、保証期限、契約の更新期限、シリアル番号、利用者といった項目を設けましょう。
入社・退職のチェックリストで漏れをゼロにする
社員の入社・退職時は、アカウントの発行や削除、端末の準備や回収など、ITに関する作業が集中します。ここで作業漏れが発生すると、新入社員がスムーズに業務を開始できなかったり、退職者のアカウントが放置されセキュリティリスクになったりします。
こうしたミスを防ぐために、誰が作業しても同じ結果になる「チェックリスト」を作成しましょう。社員が入社したときのチェックリストの内容としては、次のようなものが考えられます。
- PCのセットアップをする
- メールアカウントを発行する
- 業務に必要なSaaSへのアクセス権を付与する
- 基本的なセキュリティルールを説明する
社員が退職するときは、データやアカウントの放置を避けるため、行うべき作業のチェックリストを次のようにします。
- PC・スマホの回収(+回収すべき端末のリスト)
- すべてのアカウントの即時停止(+停止すべきアカウントのリスト)
- データのバックアップと移行
- 各種サービスの委任設定解除
社内IT相談の方法をテンプレート化する
社内のITに関する問い合わせ窓口を一本化したら、次は問い合わせの「質」を高める工夫をします。状況が正確に伝われば、それだけ解決までの時間も短縮されます。
そのために有効なのが、問い合わせ用のテンプレートの作成です。相談者は、テンプレートに情報を埋めていくだけで、必要な情報を漏れなく伝えることができます(下記、テンプレートの例)
- 相談者の氏名・部署
- 問題が発生している機器(PCの管理番号など)
- 利用しているアプリケーション名
- いつから、どのような問題が起きているか(具体的な症状)
- エラーメッセージが表示されている場合はその内容(スクリーンショット添付を推奨)
相談用のテンプレートがあれば「よくわからないけど、動かない」といった漠然とした相談が減り、必要な情報を担当者がすぐ入手できることで対応の効率が飛躍的に向上します。
さらに、問い合わせ内容を知識として蓄積するときも効率的で、FAQ(よくある質問)として整理すれば自己解決を促すナレッジベースにもなります。
月に一度の軽点検日をカレンダーに固定する
日々の業務に追われていると、どうしても後回しになりがちなのが、IT環境の定期的なメンテナンスです。そこで、毎週・毎月などのペースで「IT軽点検日」をカレンダーに固定し、習慣化してみましょう。
設定したIT回りの点検日には、下記ののような項目をチェックします。
- バックアップが正常に完了しているか
- すべてのPC・サーバーのOSやソフトウェアが最新の状態になっているか
- 使われていない休眠アカウントや、過剰な権限が残っていないか
- 各サーバーのディスク使用量や、不審な警告ログが出ていないか
月に一度、短時間でもこうした点検を行うことで、問題が大きくなる前に対処できるようになります。また、先月のトラブルを振り返り、再発防止策を検討する良い機会にもなります。
四半期ごとに確認を!IT環境のチェック項目

日々の運用や月次の軽点検に加えて、より広い視野でIT環境が健全な状態かどうか評価するタイミングを持つことが重要です。四半期ごとに、次のような項目を点検してみましょう。
- IT系のトラブルによる業務停止の頻度はどのくらいか
- 更新・バックアップ・権限見直しが後回しになっていないか
- IT担当者の休暇・退職リスクの程度はどのくらいか
- 台帳上の情報と実態がズレていないか
IT系のトラブルによる業務停止の頻度はどのくらいか
まず評価すべきは「ITが原因で業務が止まる」事態が常態化していないか、という点です。目安として月に1回以上のペースでシステムトラブルによる業務停止が見られる場合、それは単なる不運ではなく、しくみに問題があるサインかもしれません。
上記のサインを見逃さないよう、四半期ごとの点検までに「トラブルの件数や累計の停止時間」や「影響を受けた人数」を記録し、その傾向を可視化してみましょう。このとき「また同じプリンタのトラブルだ」「月末になると必ず会計システムが重くなる」といったパターンが見えてくるはずです。
更新・バックアップ・権限見直しが後回しになっていないか
日々の業務に追われ、セキュリティに関する基本的なタスクが後回しになっていないか、四半期ごとに厳しくチェックする必要があります。これらは、問題が起きてからでは手遅れになるものばかりです。
四半期ごとなどの定期点検では、社内のPCやサーバーの更新状況、バックアップの状況、休眠アカウントや不要に権限が与えられたアカウントの存在などを改めて確認しましょう。
とくにバックアップは、計画通りに成功しているかを確認するだけでは不十分です。四半期に一度は、実際にそのバックアップデータからデータを復元してみる「リストアテスト」を行いましょう。これにより、「バックアップは取っていたはずなのに、いざという時に使えなかった」という最悪の事態を防ぐことができます。
IT担当者の休暇・退職リスクの程度はどのくらいか
定期的に行う大がかりなIT総点検では、IT担当の不在・属人化によるリスクの再評価も行います。特定の兼任担当者に業務が集中しすぎている状態がないか、トラブルの対応履歴やヒアリングなどでチェックしてみましょう。
特定の担当者に業務が集中し、休暇・退職などによる混乱のリスクが大きいと判断される場合は、日頃の属人化対策をあらためて実施します。
いざという時に代行できるメンバーや、相談できる外部のバックアップ体制があるか否かも重要なチェックポイントです。可能であれば、担当者が不在の状況を想定した簡単な社内訓練を行ってみましょう。
台帳上の情報と実態がズレていないか
IT資産管理の要は「IT台帳」ですが、作成しただけで更新が滞っていては意味がありません。四半期に一度、台帳に記録されている情報と、実際に社内にある機器や利用しているサービス(実態)が一致しているかを確認する「棚卸し監査」を行いましょう。
実際にPCの台数や型番を数え、ライセンスの契約数と利用実態を突合します。このとき「台帳にはないのに使われているPC」や「誰も使っていないのに契約が続いているSaaS」など、管理の漏れや無駄が見つかることがあるかもしれません。こうしたズレは適切に、定期的に修正しましょう。
IT担当者を社内と外部のどちらで確保するか判断するときの基準
ここまで、自社でIT環境を整えるための手順を見てきました。しかし、これらの作業を継続していく中で、「やはり社内だけでは限界があるかもしれない」と感じる場面も出てくるでしょう。そのとき、次に考えるべきは「IT担当者を社内で確保し続けるのか、それとも外部の力を借りるのか」という判断です。これは、どちらが絶対的に正しいという話ではありません。会社の状況や目指す方向によって、最適な答えは異なります。ここでは、その判断を下すための「物差し」となる考え方を2つの側面から解説します。
社内で確保し続けるべきケース
まず、どのような場合にIT担当者を社内で確保し、育成していくのが望ましいのでしょうか。以下のポイントに多く当てはまるなら、内製化を目指す価値は高いと言えます。
■社内文化や業務への深い理解が不可欠な場合
……ITの役割が、単なるトラブル対応にとどまらないケースです。現場の業務フローを深く理解した上でシステム改善を提案したり、社員一人ひとりに合わせた丁寧な教育を行ったりしたい場合、社内の人間であることが強力な武器になります。
■現状の運用が安定しており、中長期的な視点でナレッジを蓄積したい場合
……大きなトラブルが頻発しておらず、月次の点検や基本的なセキュリティ対策が計画通りに進められている状態であれば、無理に外部に頼る必要性は低いかもしれません。この場合、社内でじっくりと人材を育成し、業務を通じて得た知識やノウハウを資産として蓄積していくことで、中長期的に見てコストを最適化できる可能性があります。
外部で確保したほうが良いケース
一方で、以下のような状況に陥っている場合は、積極的に外部の専門サービスの活用を検討すべきタイミングと言えます。
■トラブルが頻発し、本来業務を圧迫している場合
……「月に1回以上、ITが原因で業務が止まる」「兼任担当者が問い合わせ対応に追われ、自分の仕事が全く進まない」といった状況は、明らかに危険信号です。とくに、時間外や休日に対応できる人員がいない場合、事業継続のリスクは非常に高まります。
■属人化が進み、セキュリティや運用レベルに不安がある場合
……IT業務の属人化が進んだ先にある「あの人が辞めたら、もう誰も分からない」といった情報のブラックボックス化は、放置すればするほど深刻化します。IT担当の不在という目前のリスクに備えるためにも、ひとまず社外の信頼できるサービスを確保しておくと良いでしょう。
IT担当を社外に持つメリット

自社だけでIT環境を維持することに限界を感じたときは、外部の専門サービスを活用しましょう。外部委託は、単に「面倒な作業を丸投げする」という効果に留まらず、社内のリソースをより重要な業務に集中させ、会社全体の生産性を向上させるための戦略的な一手です。
IT担当を社外に持つ具体的なメリットとして、次のようなことがいえます。
相談窓口ができて、止まる時間が短くなる
最大のメリットは、社内のITに関する「困りごと」を一手に引き受ける専門の相談窓口ができることです。これにより、これまで兼任担当者一人に集中していた問い合わせが分散され、迅速な問題解決が期待できます。
IT業務の外注に特化したサービスでは、複数のスタッフが同時に問い合わせに対応する「並列処理」が可能です。これにより、1人が1つの問題にかかりきりになることがなくなり、問題発生から解決までの時間が大幅に短縮されます。
また、多くの場合はサービスレベルアグリーメント(SLA)によって対応時間が保証されており、時間外や休日であっても事業を止めない体制を築くことができます。蓄積された問い合わせデータを分析し、頻発するトラブルの根本原因を特定して再発防止策を提案してくれるなど、場当たり的ではない計画的な改善が進む点も大きな魅力です。
入退社や更新などの「定番作業」が自動で回る
社員の入退社に伴うアカウント設定や、定期的なソフトウェアの更新といった「定番作業」は、一つひとつは単純でも、積み重なると大きな負担になります。外部サービスは、こうした決まった業務のやり方を効率的にこなせるよう標準化し、ミスなく・迅速に処理できます。
上記のような作業を外部のIT担当に任せる直接的な効果は、社内の業務量や人員の状況に左右されることなく、決まった作業を一定の期限までに確実に実施できる点です。これにより、セキュリティレベルも常に維持されます。
セキュリティの抜け漏れを運用で防げる
IT担当がいない中小企業にとって、最も深刻な課題のひとつがセキュリティ対策です。外部の専門サービスは、最新の脅威動向や防御手法に精通しており、自社だけでは難しい高度なセキュリティ体制を構築する手助けをしてくれます。
専門家が定期的にシステムを点検し、脆弱性のチェックや修正、不審なアクセスの監視などを行うことで、セキュリティの「穴」を未然に防ぎます。万が一のインシデント発生時にも、定められた手順に沿って迅速に対応し、被害を最小限に食い止める体制が整っている点は、大きな安心材料と言えるでしょう。
人材の採用・育成リスクを下げられる
専門知識を持つIT人材の採用は、年々難しくなっており、多大なコストと時間がかかります。運良く採用できたとしても、その人材が定着するとは限らず、退職してしまえばまた探し直さなければなりません。
外部サービスを利用すれば、こうした採用や育成にかかるコストやリスクを回避し、必要なスキルを持つチームを即座に確保できます。料金は月額固定制が多いため、コストの見通しが立てやすいのもメリットです。
また「普段の運用は基本サービスでカバーしつつ、専門性が高いプロジェクトが発生したときはスポットで専門家を投入する」といった柔軟な活用も可能です。結果として、社内の貴重な人材を本来のコア業務に集中させることができ、会社全体の生産性向上に大きく貢献します。
会社規模別・IT担当の不在に強くなるための進め方
IT担当者不在の問題を解決するためのアプローチは、会社の規模や成長段階によって異なります。自社の状況に合わせて、現実的で効果的な一歩を踏み出すことが重要です。ここでは、会社の規模を3つのフェーズに分け、それぞれに適した進め方のモデルケースをご紹介します。
〜30名:棚卸し+テンプレ導入+部分的な外注から
この規模の会社では、まず自社でできる「見える化」と「ルール化」を徹底することが第一歩です。IT資産台帳や問い合わせテンプレートを導入し、多要素認証や自動更新といった基本的な設定を全社で実施しましょう。
そのうえで、すべてを自社で抱え込もうとせず、安価に利用できる小規模なヘルプデスクサービスを「お守り」として契約することをおすすめします。
30〜100名:台帳整備+入退社自動化+窓口外部化
社員数が30名を超えてくると、手作業での管理に限界が見え始めます。この段階では、MDM(モバイルデバイス管理)やIdP(IDプロバイダ)といったツールを導入し、端末の管理やアカウント設定の自動化を進めることを検討しましょう。
そして、日々発生する問い合わせの一次受付を外部サービスに委託し、社内担当者はより重要度の高い問題や、ベンダーとの調整に専念する体制を築きます。
100名〜:SLA設計+役割分担+監査とレポート運用
社員数が100名を超え、複数の拠点を持つようになると、IT運用はさらに複雑化します。このフェーズでは、社内IT部門の役割を「企画・管理」に特化させ、日々の「運用・保守」は外部に委託するという明確な役割分担が有効です。
外部サービスとは、対応時間や範囲を定めたSLA(サービスレベル合意書)を正式に結び、サービス品質を担保します。また、定期的なレポートを元に運用の改善提案を受けたり、セキュリティ監査に対応したりと、外部の専門性を活用して、より戦略的なITガバナンスを構築していく段階に入ります。
まとめ
IT担当の不在は、業務遅延、セキュリティリスクの増大、休職・退職による業務停止といった大きな問題に直結します。この見えないリスクを放置せず、まずは簡単な作業で自社のIT環境を「見える化」し、IT業務が誰かに依存しないためのルール作りを実行しましょう。
日々の運用の中で「業務が頻繁に止まる」「兼任担当者の負担が大きい」といったサインが見えてきたら、それは外部の専門サービスの活用を検討するタイミングです。
タスネットの「パワーサポート」は、まさにそうした中小企業の皆様のお悩みに応えるためのサービスです。日常のヘルプデスク業務から、専門的なセキュリティ対策、IT資産管理まで、貴社の社外IT担当として、安定した事業運営を力強く支援します。
IT環境管理業務を“まるごと”任せたい方へ
タスネットでは、お客様の状況に合わせた柔軟なITサポートサービスを提供しています。IT環境の管理業務に関するお悩みは、ぜひ一度私たちにご相談ください。



 この記事を書いた人
この記事を書いた人 関連記事
関連記事