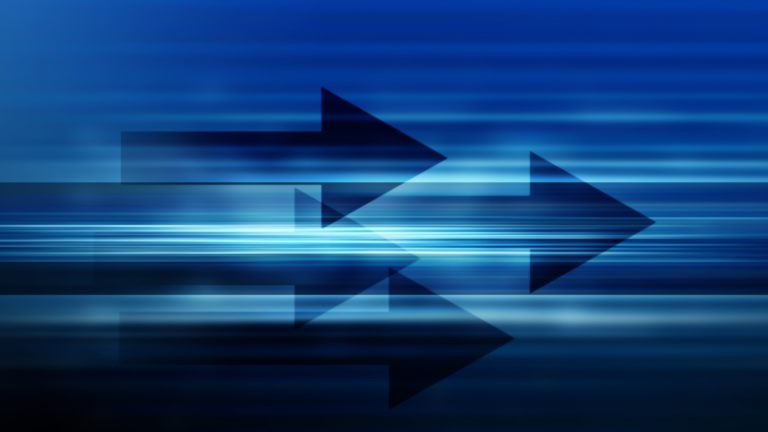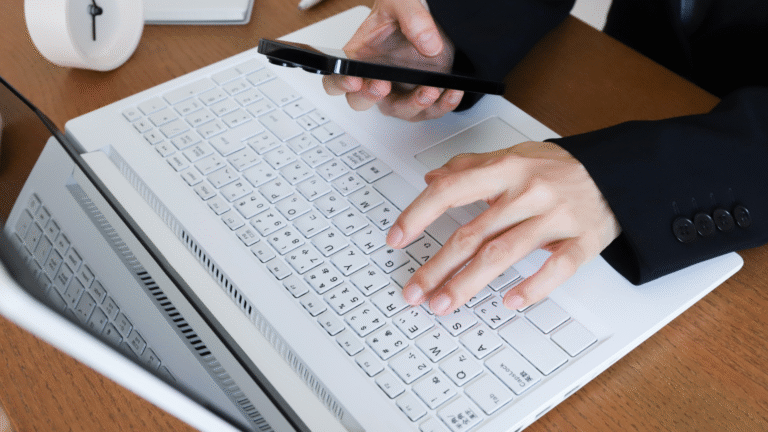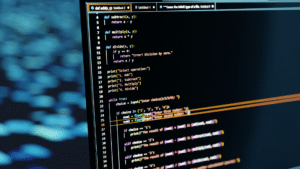Column オフィスITのお役立ちコラム
ITのお悩み・最新トレンドをやさしく解説。
業務に役立つノウハウを発信しています。
2025.07.10
中小企業のセキュリティ課題とは?現状から解決策まで徹底解説
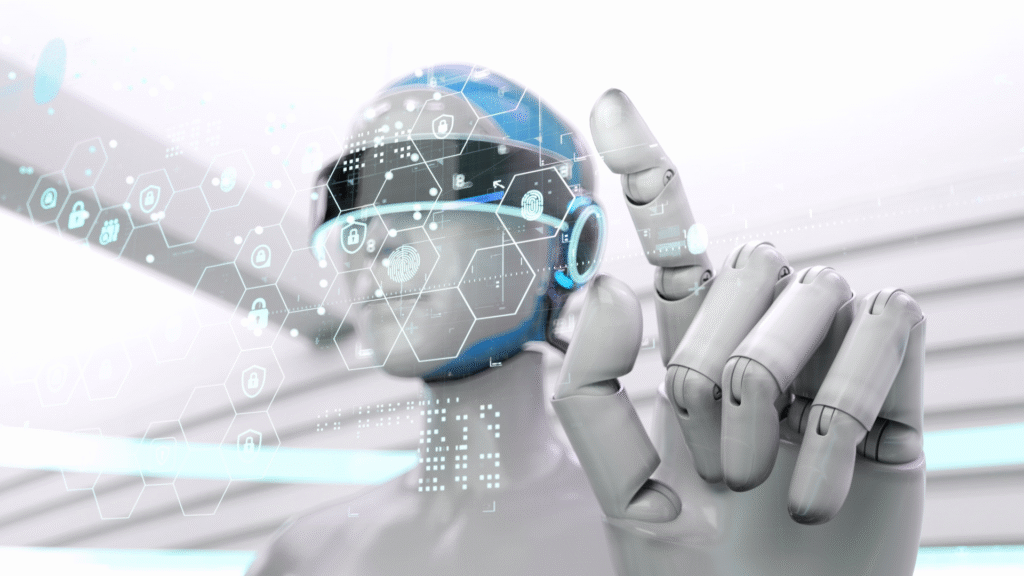
デジタル化が加速する現代、サイバー攻撃の脅威は大企業だけでなく中小企業にも及んでいます。限られた人材や予算の中で日々の業務をこなす中小企業にとって、セキュリティ対策は後回しになりがちですが、情報漏洩や業務停止のリスクは決して小さくありません。
ここでは、中小企業が直面するセキュリティ課題の現状とその背景、そして実践的な解決策までをわかりやすく解説します。経営者やIT担当者が今すぐ取り組むべきポイントを整理し、安心して事業を継続するためのヒントをお届けします。
中小企業が直面するセキュリティ課題の現状
デジタル化が進む中、サイバー攻撃の標的は大企業だけでなく中小企業にも広がっています。中小企業は限られたリソースや人材で日々の業務を回しているため、セキュリティ対策が後回しになりがちです。しかし、取引先や顧客情報を扱う以上、情報漏洩や業務停止のリスクは無視できません。
中小企業のセキュリティ対策の実態
中小企業では大企業と比べてセキュリティ対策の遅れが目立ち、組織的な体制が整備されていない企業も多い状況です。
情報処理推進機構(IPA)の調査では、OSやウイルス対策ソフトの最新化を実施している企業は約7割に達していますが、専任のセキュリティ担当者を配置している企業は少数にとどまります。予算配分も十分とは言えず、必要な対策を十分に講じられない現実が浮き彫りになっています。
※参考:IPA(情報処理推進機構)「中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」速報版
サイバー攻撃被害の発生件数と影響
サイバー攻撃の被害は年々増加傾向にあり、2024年にはランサムウェア攻撃の被害件数の約6割が中小企業で発生しました。被害額は100万円から1000万円未満が最も多く、全体の37%を占めています。
復旧対応には多大な費用と時間がかかり、業務停止による機会損失も深刻です。さらに、顧客情報が漏洩した場合は損害賠償リスクも発生し、企業の信頼失墜につながる恐れがあります。
※参考:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(警察庁)
セキュリティ対策を阻むもの(人・予算・情報の不足)
中小企業がセキュリティ対策を進める上で最大の障壁となっているのは、専門人材の不足です。限られた予算の中でコストを抑えたいという意識も根強く、経営層のセキュリティ意識が十分でないケースも少なくありません。
対策の遅れにつながっているほかの要因として、自社は狙われないという思い込みや、何から始めればよいか分からない情報不足も挙げられます。こうした要因が重なり、十分なセキュリティ体制の構築が難しい現状です。
セキュリティ対策が必要となるきっかけ
セキュリティ対策を本格的に検討するきっかけとして、取引先からのセキュリティ強化要請が挙げられます。また、実際にインシデントが発生した経験や、個人情報保護法など法規制への対応が求められる場面も増えています。
テレワークの普及により新たなリスクが顕在化し、同業他社の被害事例を知ったことで危機感を持つ企業も多くなっています。これらの要因が、セキュリティ対策の必要性を強く意識させる契機です。
中小企業が対応すべき具体的なセキュリティ課題

デジタル化やテレワークの普及により、中小企業も高度なセキュリティ対策が求められる時代となりました。しかし、限られたリソースや専門知識の不足から、十分な対策が後回しになりがちです。
ここでは、中小企業が優先的に取り組むべき具体的なセキュリティ課題について、技術面・人材面・物理面の観点から整理します。自社の現状を見直し、段階的な対策を進めることが重要です。
基本的な技術的対策を確認する
サイバー攻撃の多くは、基本的な技術対策の不備を突いて発生します。まず、ウイルス対策ソフトの導入と定期的な更新は必須です。ファイアウォールの設置により、外部からの不正アクセスを遮断しましょう。OSやアプリケーションのソフトウェア更新を怠らず、脆弱性を常に修正するのも大切です。
セキュリティ情報へのアクセスについては、パスワードは複雑かつ定期的に変更し、使い回しを避けるよう周知すべきです。アクセス権限の管理の徹底も欠かせません。
従業員のセキュリティ意識を向上させる
技術的な対策だけでなく、従業員一人ひとりの意識向上も不可欠です。まず、社内で守るべきルールを明文化したセキュリティポリシーを策定しましょう。従業員教育は定期的に実施し、最新の脅威や注意点を共有します。
啓発に繋げるため、年に数回のセキュリティ研修や、実際のフィッシングメールを使った訓練も効果的です。同時に、従業員のセキュリティ意識を定期的に調査し、弱点を把握して改善策を講じると良いでしょう。
物理的なインシデントを防止する
サイバー攻撃だけでなく、物理的なリスクにも目を向けなくてはなりません。まずは、オフィスやサーバールームへの入退室管理の徹底や、施錠可能なキャビネットや金庫での情報保管、不要になった機密文書のシュレッダー廃棄の徹底などといった措置を講じるべきです。
セキュリティインシデント発生時の対応手順
サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティインシデントは、どの企業にも起こり得るリスクです。とくに中小企業は、被害が発生した際の影響が大きく、迅速かつ的確な対応が求められます。
ここで解説するのは、インシデント発生時に取るべき基本的な対応手順です。日頃から備えを徹底し、万一のときの被害を最小化できるようにしましょう。
初動対応の重要性
インシデント発生時は、まず異常をいち早く検知する仕組みが不可欠です。検知後は、あらかじめ定めた対応体制を迅速に立ち上げ、関係者が役割分担を明確にして動きます。
被害状況の把握では、どのシステムやデータが影響を受けているかを正確に確認することが重要です。証拠保全も忘れてはならず、ログやファイルのコピーを確保しておくことで、後の原因究明や法的対応に役立ちます。対応の経過や判断内容は、必ず記録として残しておきましょう。
被害拡大防止のための緊急措置
被害が広がるのを防ぐため、ネットワークの一部または全体を遮断する判断が必要になる場合があります。感染が疑われる機器は速やかにネットワークから隔離し、ほかの端末への拡大を防ぎます。
このとき、システム全体の停止が必要かどうかは、業務への影響と被害範囲を見極めて適宜判断しなければなりません。少なくとも、外部からの不正アクセスが続いている場合は、ファイアウォールやVPNの設定を見直し、遮断措置を講じます。
関係者への報告と連絡体制
インシデント発生時は、まず経営陣に状況を正確に報告し、意思決定を仰ぎます。取引先への連絡は、被害の内容や影響範囲を把握したうえで、適切なタイミングで行うことが信頼維持につながるでしょう。
個人情報が漏洩した場合などは、監督官庁への届出が法的に義務付けられているケースもあるため、速やかな確認と対応が必要です。顧客への情報開示は、混乱を避けるためにも事実関係を整理したうえで行います。
復旧作業と再発防止策
復旧作業では、まずシステムやサービスの中で優先度の高いものから順に復旧を進めます。データの復旧は、バックアップデータの整合性を確認しながら慎重に行うことが求められます。
業務再開の判断は、セキュリティリスクが十分に排除されたことを確認したうえで行いましょう。インシデントの原因となった脆弱性については、修正対応を徹底し、同様の被害が再発しないよう対策を講じます。
外部委託を活用したセキュリティ課題の解決方法

中小企業にとって、限られた人材や予算の中で高度なセキュリティ対策を自社だけで完結するのは難しい現実があります。サイバー攻撃の手口が日々進化する中、専門知識や最新の脅威情報を常にキャッチアップするのは容易ではありません。
こうした背景から、外部の専門業者にセキュリティ対策を委託する企業が増えています。外部委託を活用することで、効率的かつ効果的にセキュリティレベルを高めることが可能となります。
外部委託が解決するセキュリティ課題とは
外部委託の最大のメリットは、社内に専門人材がいなくても高度なセキュリティ対策を実現できる点です。専門業者は24時間365日の監視体制を持ち、インシデントの早期発見と迅速な対応が可能です。
また、最新の脅威情報や攻撃手法にも精通しており、自社だけでは気づきにくいリスクにも対応できます。自社で人材を採用・育成するよりもコスト効率が良く、必要なサービスだけを選択できる柔軟性も魅力です。
セキュリティ業者選定のポイント
- 中小企業向けの導入実績が豊富かどうか
- 保有資格や第三者認証(ISO27001など)の有無
- 担当技術者のスキルや経験、業界特有の知見
- 技術やサービスの継続的な向上への取り組み
- 緊急時・日常サポート体制、問い合わせ対応の明確さ
- サービス内容と費用のバランス、契約条件の明確さ
委託範囲の決め方と注意点
外部委託を進める際は、まず自社で保持すべき業務と委託する業務を明確に切り分けることが重要です。最初から全てを委託するのではなく、段階的に範囲を拡大していく方法も有効です。業者への依存度が高くなりすぎないよう、定期的に契約内容やサービスの質を見直しましょう。
セキュリティ対策が企業に与えるメリット
サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる中、セキュリティ対策は単なる防御策にとどまりません。適切な対策を講じることで、企業は取引先や顧客からの信頼を獲得し、事業の安定運営や競争力の強化にもつなげることができます。
取引先からの信頼向上
セキュリティ認証の取得は、他社との差別化を図る有効な手段です。とくに大手企業との取引を目指すときには、情報セキュリティの体制が整っていることが前提となるケースが少なくありません。
サプライチェーン全体でのセキュリティ要求が高まる中、対策の強化は契約条件の改善や新規取引の獲得に直結するタスクです。確実に実行することで、長期的な信頼関係の構築にも寄与し、安定したビジネス展開が可能となります。
事業継続性の確保
システム障害やサイバー攻撃による業務停止リスクを軽減できるのも、セキュリティ対策の大きなメリットです。定期的なバックアップや多層的な防御策により、データ消失や業務中断を未然に防ぐことができます。
万が一トラブルが発生しても、迅速な復旧が可能となり、顧客サービスの継続提供が実現します。こうした備えが、事業計画の安定性向上にも直結します。
競争優位性の獲得
セキュリティ対策を強化することで、営業活動においても大きな武器となります。業界内での差別化要因となり、新規顧客の獲得やブランドイメージの向上に寄与します。
市場での信頼性が高まることで、他社よりも有利な立場でビジネスを展開できるようになります。このように、セキュリティを経営戦略の一部として活用する企業が増えています。
従業員の安心感向上
安全な職場環境を整えることで、従業員は安心して業務に取り組むことができます。情報漏洩による個人責任のリスクが軽減され、働きやすい環境が実現します。
こうした取り組みは従業員のモチベーション向上や人材の確保・定着率の改善にもつながるでしょう。組織全体の生産性向上にも好影響をもたらします。
まとめ
中小企業にとってセキュリティ対策は、もはや選択肢ではなく必須の経営課題です。人材や予算の制約があっても、基本的な技術対策や従業員教育、物理的な管理を着実に進めることでリスクを大きく減らすことができます。さらに、外部の専門業者を活用することで、最新の脅威にも柔軟に対応できる体制を構築することが可能です。
セキュリティ対策を強化することは、取引先や顧客からの信頼獲得、事業の安定運営、そして企業の成長にも直結します。自社の現状を見直し、できることから一歩ずつ取り組んでいきましょう。セキュリティに関するご相談や具体的な対策のご提案は、ぜひタスネット社までお気軽にお問い合わせください。
中小企業のセキュリティ業務を“まるごと”任せたい方へ
当社の オフィスITサポートは、
インフラ整備・人材不足・属人化など
中小企業のセキュリティ課題をワンストップで解決します。
まずはサービス内容をチェックして、自社にフィットするかご確認ください。



 この記事を書いた人
この記事を書いた人 関連記事
関連記事