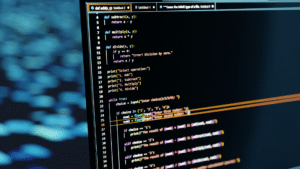Column オフィスITのお役立ちコラム
ITのお悩み・最新トレンドをやさしく解説。
業務に役立つノウハウを発信しています。
2025.10.10
ITヘルプデスクとは?役割や運用・外注のポイントを解説

ITヘルプデスクとは、社内の従業員から寄せられるパソコンやインターネット環境に関する質問に対応し、IT周りのトラブルを解決する役割を担う窓口です。そのほか、IT資産の管理や、セキュリティ周りの運用・管理を業務範囲に含める場合もあります。
ここでは、ITヘルプデスク導入のメリットや、そこに生じる課題、そして外注する場合のポイントを解説します。
企業活動で必要なITヘルプデスクとは
会社の活動におけるITヘルプデスクは、社内のITに関する「困った」を一手に引き受ける専門の窓口です。パソコンやソフトウェア、インターネット環境などのトラブルについて問い合わせに対応し、解決することで、会社の活動が止まらないようにする役割を担います。
ITヘルプデスクの主な役割
ITヘルプデスクの基本的な役割は、ほかの従業員からのITに関するあらゆる問い合わせに対応する窓口となることです。問い合わせの中心となるのは、下記のようなトラブルです。
- パスワードを忘れた
- ソフトの使い方がわからない
- インターネットがつながらない
- パソコンもしくはソフトが起動しない
上記のような問い合わせがITヘルプデスクのもとに入ったときは、まず知識を駆使して原因を特定する作業を行います。最終的な目的は、問い合わせ元の業務をなるべく止めないよう、短時間で問題を解決することです。
このように、ITヘルプデスクの役割は「単に受け身で質問に答えるだけ」ではありません。会社のITインフラ全体が常に安定して稼働するよう、見守り、支える役割も担っているのです。
中小企業にITヘルプデスクが必要とされる理由
近年、多くの中小企業でITヘルプデスクの重要性が高まっています。その背景にあるのは、業務効率化のためのDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展です。
社内の業務をアナログからデジタルに置き換えるため、新しいクラウドサービスやアプリケーションを導入すると、パソコンなどの操作機器の設定は高度化・複雑化します。こうなると、操作にある程度慣れている従業員が揃った業務でも「操作方法がわからない」「うまく起動しない」といったトラブルは避けられません。
上記のようなトラブルの増加には、知識を持ち、特化して業務にあたる「ITヘルプデスク」の存在が効きます。
ITヘルプデスクの業務内容

ITヘルプデスクの仕事は、実のところ、社員からの質問に答えるだけではありません。下記のように業務は多岐にわたり、会社のIT環境を裏側から支える重要な役割を担っています。
- 社員からの問い合わせ対応
- 社内にあるIT資産の管理
- オンボーディング支援
- セキュリティ対策の運用・管理
社員からの問い合わせ対応
ITヘルプデスクの業務の中心になるのは、社員からの問い合わせ対応やトラブルシューティングです。改めて問い合わせ内容をカテゴリーで分けると、次のようなものが挙げられます。
- パソコンなどの操作方法に関する質問
- 起動・インターネット接続のトラブル対応
- ソフトウェアのアップデートに関する質問
- セキュリティに関する質問(アカウントのログイン権限など)
社内にあるIT資産の管理(パソコンやソフトウェアなど)
IT資産の管理も、ヘルプデスクの仕事となることがよくあります。管理する資産には、物理的な資産(パソコンなど)だけでなく、端末の内部にある電子的な資産(ソフトウェアのライセンスなど)も含まれます。
- パソコンの台数とスペック
- スマートフォンの台数とスペック
- パソコン・スマートフォンの利用状況
- 使用するソフトウェアのライセンス数
- リース契約の前回更新日、更新期限、価格
オンボーディング支援(アカウント発行やキッティングなど)
社員の入退社に伴うサポートは、ITヘルプデスクが担う例が多く見られます。新入社員や中途採用者が入社したときは業務開始のための端末準備を、退社したときは社員が使っていた端末の回収を行います。
- PCの初期設定(キッティング)
- 各種システムを利用するためのアカウント発行
- ITツールの基本的な使い方を説明するオリエンテーション
- 貸与が終わった端末の回収
- 利用されなくなったデータのバックアップ
- 利用されなくなったアカウントの削除
セキュリティ対策の運用・管理
企業の情報を守るセキュリティ対策の運用・管理も、ときとしてITヘルプデスクの仕事となります。ハッキングに遭わないための情報管理だけでなく、各種システムを更新して最新のセキュリティ対策を反映させるのも重要だとされます。
- 使われなくなったアカウントの削除
- ウイルス対策ソフトの導入・更新
- 各種システムの修正プログラム(セキュリティパッチ)の導入
- セキュリティルール(受信したメールの対応など)に関する全社周知
社内ITヘルプデスクのよくある課題
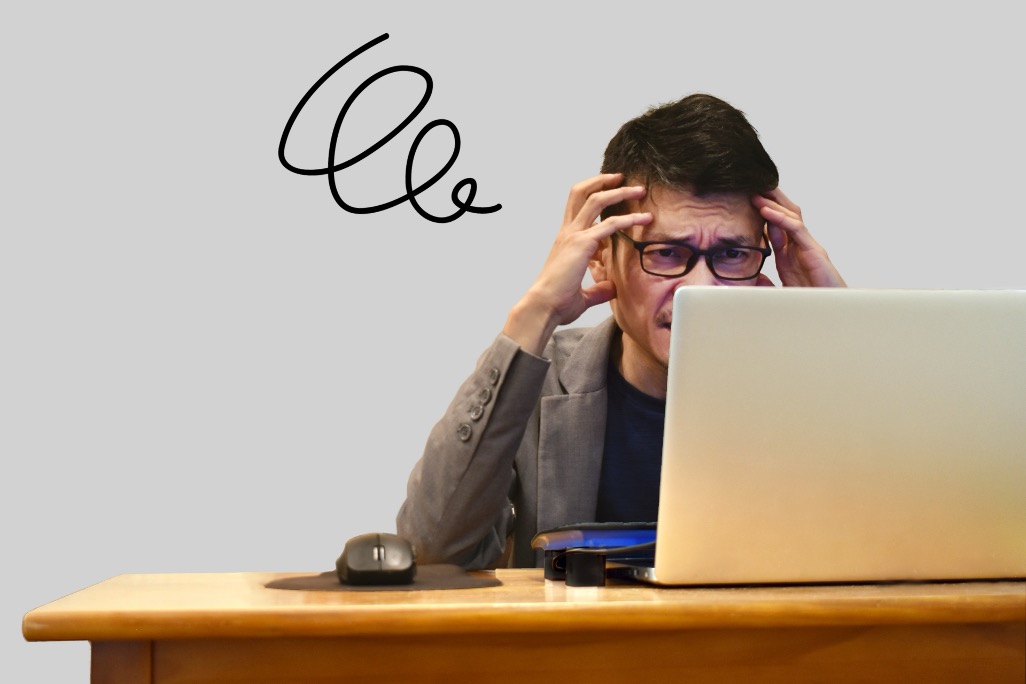
社内のITヘルプデスクは、トラブル対処などを通じて会社の生産性向上につながる一方、運用上の課題に直面することも少なくありません。人やノウハウが揃っている会社でないと、担当者を置き続けるのは難しいといわざるを得ないでしょう。
ヘルプデスク役の社員が1人しかいない
よくあるのは、ITヘルプデスク役になれる社員が1人しかいないケースです。この担当者が急に休んだり、退職してしまったりすると、社内のITサポートが完全に停止し、業務に大きな支障をきたしかねません。
また、業務負荷が一人に集中するため、担当者自身が疲弊し、心身の不調につながる「燃え尽き症候群」に陥るリスクが大きくなります。日々の問い合わせ対応に追われ、新しい技術を学んだり、より戦略的なIT活用を検討したりする時間を確保できないことも、会社にとって大きな損失です。
質問対応で本来の業務が止まる
兼任のITヘルプデスク役しかいないケースでは、質問対応で本業が回らなくなってしまう可能性が考えられます。突発的に発生する社員からの問い合わせによって、集中して取り組んでいた本業が何度も中断されるのも困りものです。
上記のような状況が続けば、やがて納期や会社の事業計画全体に影響するでしょう。残業の増加などにより、人件費増加だけでなく、社員の満足度にも悪影響を与えてしまう可能性も考えられます。
IT知識やトラブル事例の引き継ぎが進まない
ITヘルプデスクを設置し続ける場合の課題として、ノウハウや事例の蓄積・引き継ぎが挙げられます。担当者が日々の業務に追われていると、メモ・マニュアル・手順書などをまとめる時間を確保するのは困難です。その一方で、記録がないと将来の対応に影響が生じます。
過去に解決したはずのトラブルが再発した際には、またゼロから調査を始めるとなると、時間と人件費の無駄になります。担当者が退職などでいなくなったときも、知識・事例の蓄積がないと、同じように生産性を下げる結果となるでしょう。
新しいシステムやアプリケーション導入の際に混乱が起きる
ITヘルプデスクがいたとしても、業務効率化のために新しいITツールを導入した場合、そのせいで大きな混乱を招くことがあります。とくに兼任のIT担当者の場合、導入前の十分な準備や、変更点に関する社内への丁寧な事前告知まで手が回らない点に注意しなければなりません。
操作方法に関する問い合わせがヘルプデスクに殺到して担当者がパンクすると、最悪の場合には会社全体の業務を停止せざるを得ません。準備・告知の期間を十分に取れない場合、ヘルプデスクが要をなさないといえます。
ITヘルプデスクが抱える課題を解決する方法
社内のITヘルプデスクが抱える課題は、少しの工夫で解決できます。ここで紹介する対応ができるよう準備や改善を進めることで「いつでもスムーズに機能するヘルプデスク」を構築できるでしょう。
問い合わせ前に確認できるFAQを整備する
同じような質問が何度も寄せられるのは、対応する側にとって非効率的です。なるべくITヘルプデスクの運用開始直後から、過去に寄せられた質問とその回答をまとめた「よくある質問集(FAQ)」を作成しましょう。
完成したFAQは、社員がいつでも自分で確認できるように、社内ポータルサイトや共有フォルダといったアクセスしやすい場所に掲載するとよいでしょう。さらに、定期的に内容を見直し、情報が古くなっていたら削除・更新していくことで、FAQは常に役立つ「自己解決のための辞書」として機能します。
問い合わせ管理ツールで対応をスムーズにする
メールや口頭での問い合わせ管理には限界があります。ITヘルプデスクには、専用の「問い合わせ管理ツール」を導入することで、すべての問い合わせをひとつの画面で受け付け、
- 誰がどの案件を対応しているのか
- 進捗状況はどうなっているのか
を一元管理できます。こうしたツールの導入は、対応漏れや二重対応といったミスを防ぎ、ヘルプデスクの品質を均一にするでしょう。
ツールに蓄積されたデータを分析すれば、「どの部署から」「どのような問い合わせが多いか」といった傾向を把握し、より根本的な業務改善に役立てることも可能です。
ヘルプデスク対応のルールを決めて、誰でもできるようにする
担当者の経験や勘に頼った運用は属人化を招きます。ITヘルプデスク業務を「誰でもできるようにする」にあたって、対応ルールの明確化が不可欠です。
手始めにできるのは、簡単なトラブルシューティングの手順書や、対応完了時のチェックリストを用意することです。これらは新任のITヘルプデスクや、必ずしも専門的な知識を持っているとは限らない兼任担当者の「知識の源」になるでしょう。
ほかには、担当者だけでは解決できない場合に、誰に、どのように相談・報告するかのフロー(エスカレーションルール)を定めておくのも良い方法です。エスカレーション先で緊急度を判断して優先対応案件を決めるなど、対応の効率化に繋がります。
外注(アウトソーシング)を検討する
社内のリソースだけではどうしても対応が追いつかない場合、業務の一部を専門業者に委託する外注(アウトソーシング)も良い選択肢です。
例として、パスワードリセットなどの定型的・反復的な問い合わせ対応を外部に任せることで、社内のIT担当者は、より専門性が高く・会社の成長に直結する業務に集中できるようになります。ほかには、社内担当者ではカバーしきれない定時外のサポートを依頼する方法が考えられます。
ITヘルプデスクを社外にアウトソーシングする最大のメリットは、対応品質と効率が保証される点です。社内教育やナレッジ蓄積の手間がなくなり、本業に集中できます。
ITヘルプデスクを外注(アウトソーシング)する際のポイント
社内だけでの対応に限界を感じたとき、ITヘルプデスク業務の外注(アウトソーシング)は非常に有効な解決策となります。しかし、ただ丸投げするだけでは成功しません。自社の状況に合った委託先を選び、任せる業務範囲を明確にするようにしましょう。
外注するITヘルプデスク業務とその範囲を決める
アウトソーシングを成功させる鍵は「何を」「どこまで」任せるかを明確にすることです。
まずは、社内リソースの現状分析から始めましょう。IT担当者のスキルや、日々の業務量、とくにどのような問い合わせに時間を取られているかを把握します。その上で、パスワードリセットや定型的な申請手続きなど、マニュアル化しやすい業務かどうかを見極めます。こうした業務は外注しやすい領域です。
最初から多くの業務を外注するのに不安がある場合は、まずは問い合わせ対応の一部など、限定的な範囲からスモールスタートするのがおすすめです。効果を見ながら段階的に範囲を広げていくと失敗が少なくなります。
外注先選定でチェックすべき項目
アウトソーシング先を価格だけで選んでしまうと「安かろう悪かろう」となりかねません。下記のように、実績、対応力、専門性、セキュリティ体制、報告・改善提案の5つの視点で考えると良いでしょう。
■実績
……自社の業種や企業規模に近い会社のサポート実績が豊富かを確認しましょう。実績が多ければ、特有の課題にもスムーズに対応できる可能性が高いといえます。
■対応力
……サポート時間は自社の就業時間やビジネススタイルに合っているか(例:24時間365日対応可能か)、電話・メール・チャットなど希望の対応チャネルが用意されているか、といった点は重要です。
■専門性
……ITサービスのベストプラクティスに関する知識を持つスタッフが在籍しているかなど、技術レベルや専門性を確認します。これにより、対応の品質がある程度担保されます。
■セキュリティ体制
……会社の情報を預ける以上、セキュリティ体制は最も重要なチェック項目の一つです。情報セキュリティに関する第三者認証を取得しているかは、信頼できる業者かを見極める客観的な指標となります。
■報告・改善提案
……単に依頼された業務をこなすだけでなく、対応状況を定期的にレポートとして提出し、問い合わせ傾向の分析から「FAQを充実させましょう」といった業務改善提案までしてくれるパートナーかどうかも見極めましょう。
まとめ
機能するITヘルプデスクは、日々のITトラブルから従業員を解放し、誰もが安心して本来の業務に集中できる環境を作るために不可欠です。しかし、FAQ整備やルールの策定など、社内リソースだけで万全の体制を整えるのは容易ではありません。
「何から手をつければいいかわからない」「IT担当者の負担を今すぐ減らしたい」とお悩みなら、専門家へのアウトソーシングを検討してみませんか。
タスネットの「オフィスITサポート」は、貴社のITヘルプデスクとして、日々の問い合わせ対応からIT環境の整備まで幅広く代行します。まずはお気軽に資料請求、またはお問い合わせください。
ITヘルプデスクの管理業務を“まるごと”任せたい方へ
タスネットでは、お客様の状況に合わせた柔軟なITサポートサービスを提供しています。IT環境の管理業務に関するお悩みは、ぜひ一度私たちにご相談ください。



 この記事を書いた人
この記事を書いた人 関連記事
関連記事